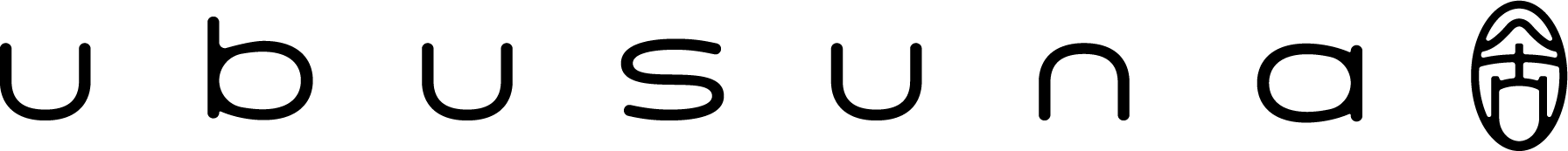共
創
の仲間
UBUSUNA TESHIGOTO CoWORKING
山鹿市 煤竹のボタン|木部大資
SUSUDAKE BUTTON DAISUKE KIBE
山鹿市
煤竹のボタン|木部大資
SUSUDAKE BUTTON DAISUKE KIBE
幾星霜を経た煤竹の、えも言われぬ艶と色味
幾星霜を経た煤竹の、えも言われぬ艶と色味
山鹿の高台に建つ古民家に、竹細工作家、木部大資のアトリエがある。ここは、かつて祖父が畳屋を営んでいた場所。10年ほど空き家になっていたが、なんらかの形で活かすことができないかと、木部の母親は考えた。そこで、リフォームしていた部分を取り除いてみると、江戸末期に建てられた町家が、昔のままの家が姿を現したのだった。町家の手前部分は『古民家ギャラリー 百花堂』として、さまざまな展示イベントに使用。木部の仕事場は、その奥にある、祖父が畳作りの際に使っていた小屋である。
木部が竹細工を始めたのは、17歳の頃。 「自分の気に入る箸や耳かきがなかったので、自作するようになりました。祖父が、趣味で竹を使って鳥籠などを作っていたので、竹細工自体は身近なものでした」と木部は振り返った。 現在、彼が日々向き合っているのは、50年から100年の間、囲炉裏や竈の煙で燻されてきた煤竹。元は茅葺き屋根の骨組みとして使われてきたものである。 「普通の竹とは違い、飴色に染まった表面には、独特の艶があります。見た目が美しいのはもちろん、丈夫でカビが生えにくいのも特長です」と木部は煤竹の魅力を語る。 しかし、煤竹を入手するのは決して容易ではない。基本的には、古い家を壊したり、修理した時にしか出てこない。いろんな人に予め声をかけており、「ご縁があったらいただく」のだそうだ。 ギャラリーも営んでいる関係で、工芸家や美術関係者と出会う機会もあった。彼らから様々なことを学んでいくうちに、木部自身の美意識も磨かれ、作る作品の幅も広がったのであった。今では、創作活動のきっかけとなった箸や耳かきに加えて、茶杓などの茶道具のほかに竹のオブジェなども手がけている。 しかし、本人が最もこだわっているのは、やはり箸や耳かきといったシンプルなものだ。
「お箸の形は最も単純ですよね。でも、何本作っても、完璧なものができたと思えない。その時、その時で、使う煤竹の状態や形状は異なります。毎回、目の前の竹の個性を活かし、美しく見えるように、箸を削り出していくのですが、出来上がると、もっと良いものができるんじゃないかという気持ちが湧いてきます。だから、毎日、飽きることなく作業台に向かえるんだと思います」 木部の箸は着実にファンを増やしている。「この箸じゃないとダメ」と言う中学生もいるそうだ。 「そんな声を聞くと、本当に嬉しくなりますね」 実際に木部の作った箸を手に取ってみる。軽いのは当たり前だが、見た目も優美で手に馴染む。そして、太い部分でも7ミリに満たない箸の表面には、その竹の個性が、確かに息づいている。 今回、ubusuna IZA prototype のために制作した煤竹ボタンは、かなり小さいものなので、竹の模様や形といった個性は省かれてしまう。それでも、木部は、それぞれの竹の特性を見極め、ゆっくりと小刀で削っていく。やがてボタンに現れる繊細な表情は、機械では決して再現することはできないだろう。(2024年10月31日時点での記事)
山鹿の高台に建つ古民家に、竹細工作家、木部大資のアトリエがある。ここは、かつて祖父が畳屋を営んでいた場所。10年ほど空き家になっていたが、なんらかの形で活かすことができないかと、木部の母親は考えた。そこで、リフォームしていた部分を取り除いてみると、江戸末期に建てられた町家が、昔のままの家が姿を現したのだった。
町家の手前部分は『古民家ギャラリー 百花堂』として、さまざまな展示イベントに使用。木部の仕事場は、その奥にある、祖父が畳作りの際に使っていた小屋である。 木部が竹細工を始めたのは、17歳の頃。 「自分の気に入る箸や耳かきがなかったので、自作するようになりました。祖父が、趣味で竹を使って鳥籠などを作っていたので、竹細工自体は身近なものでした」と木部は振り返った。 現在、彼が日々向き合っているのは、50年から100年の間、囲炉裏や竈の煙で燻されてきた煤竹。元は茅葺き屋根の骨組みとして使われてきたものである。
「普通の竹とは違い、飴色に染まった表面には、独特の艶があります。見た目が美しいのはもちろん、丈夫でカビが生えにくいのも特長です」と木部は煤竹の魅力を語る。 しかし、煤竹を入手するのは決して容易ではない。基本的には、古い家を壊したり、修理した時にしか出てこない。いろんな人に予め声をかけており、「ご縁があったらいただく」のだそうだ。 ギャラリーも営んでいる関係で、工芸家や美術関係者と出会う機会もあった。彼らから様々なことを学んでいくうちに、木部自身の美意識も磨かれ、作る作品の幅も広がったのであった。
今では、創作活動のきっかけとなった箸や耳かきに加えて、茶杓などの茶道具のほかに竹のオブジェなども手がけている。 しかし、本人が最もこだわっているのは、やはり箸や耳かきといったシンプルなものだ。 「お箸の形は最も単純ですよね。でも、何本作っても、完璧なものができたと思えない。その時、その時で、使う煤竹の状態や形状は異なります。毎回、目の前の竹の個性を活かし、美しく見えるように、箸を削り出していくのですが、出来上がると、もっと良いものができるんじゃないかという気持ちが湧いてきます。だから、毎日、飽きることなく作業台に向かえるんだと思います」 木部の箸は着実にファンを増やしている。「この箸じゃないとダメ」と言う中学生もいるそうだ。 「そんな声を聞くと、本当に嬉しくなりますね」 実際に木部の作った箸を手に取ってみる。軽いのは当たり前だが、見た目も優美で手に馴染む。そして、太い部分でも7ミリに満たない箸の表面には、その竹の個性が、確かに息づいている。
今回、ubusuna IZA prototype のために制作した煤竹ボタンは、かなり小さいものなので、竹の模様や形といった個性は省かれてしまう。それでも、木部は、それぞれの竹の特性を見極め、ゆっくりと小刀で削っていく。やがてボタンに現れる繊細な表情は、機械では決して再現することはできないだろう。(2024年10月31日時点での記事)






200年以上前の古民家で見つかった煤竹
200年以上前の古民家で見つかった煤竹
煤竹のボタンは、ubusuna iza prototypeのシャツの襟元と両手首のカフスに使われている。木部大資氏が、煤竹を一つ一つ手作業で四角に切り出し削って、ボタンに仕立て上げた。使われている煤竹は、200年以上前、江戸時代に建てられた古民家で見つかったもの。その古民家は、2023年に国宝に指定された通潤橋から車で30分ほどの場所にあり、2022年からカフェとして営業している。
煤竹のボタンは、ubusuna iza prototypeのシャツの襟元と両手首のカフスに使われている。木部大資氏が、煤竹を一つ一つ手作業で四角に切り出し削って、ボタンに仕立て上げた。使われている煤竹は、200年以上前、江戸時代に建てられた古民家で見つかったもの。その古民家は、2023年に国宝に指定された通潤橋から車で30分ほどの場所にあり、2022年からカフェとして営業している。

古民家ギャラリー百花堂
熊本県山鹿市山鹿1371(古民家ギャラリー百花堂) 木部 大資(きべ だいすけ)
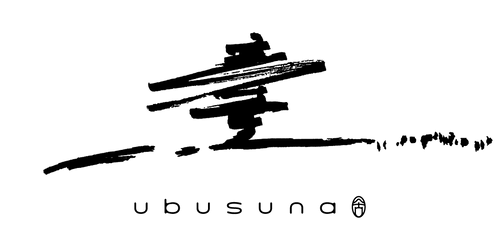
© ubusuna 2024 Furushohonten