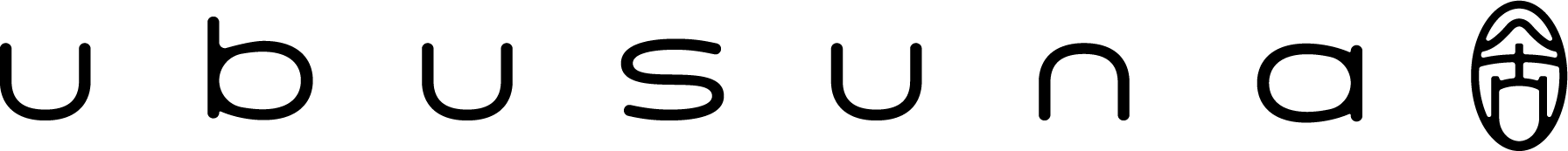共
創
の仲間
UBUSUNA TESHIGOTO CoWORKING
水俣市 水俣浮浪雲工房
MINAMATA HAGUREGUMO KOUBOU
水俣市
浮浪雲工房
MINAMATA HAGUREGUMO KOUBOU
脈々と受け継がれてきた手仕事が、新しい文化を生む
脈々と受け継がれてきた手仕事が、新しい文化を生む
水俣浮浪雲工房は、手漉き和紙と草木染めの手織り布を主に製造している。ある日工房を訪ねると、土間では代表の金刺潤平が昔ながらの道具で紙を漉いていて、奥の部屋からは「タンタン」という音が聞こえてきた。潤平のパートナーでもある金刺宏子が機を織っている音だ。 この工房は、胎児性及び幼児性水俣病患者に生きる糧を与えることを目的に1982年に創設された、自給自足型のフリースクール、水俣生活学校が原型である。
潤平は、東京の大学を卒業すると同時に、ボランティアとして水俣生活学校に参画するために水俣の地を踏んだ。紙漉きを始めたのは、詩人、作家、そして環境運動家として知られる石牟礼道子氏のアドバイスによるものだ。 「水俣病の子供達でもできる仕事を作るという一念で紙漉きを始めたのですが、それではなかなかお金は稼げないわけですよ。そんななか、道子さんは、いろんな面で、ずっと活動をサポートしてくれました。僕らが自分たちの手仕事で生きていけるようになって、一番喜んでくれたのも道子さんでした」 それから時が流れた2015年、潤平は、石牟田氏の推薦により、当時の天皇皇后両陛下がご使用になった和紙のグリーティングカードを制作している。
潤平は紙漉き以外にもイノベイティブな才能を発揮。イグサの製紙原料繊維化技術に成功したほか、立体紙を考案したりと仕事のフィールドを広げてきた。また、ウズベキスタン・サマルカンドのシルクペーパーの復元など、その活動の場は国境をも越えている。 それでも彼は、今日も水俣の地で紙を漉く。それは、作家、水上勉氏にかけられた一言が心に刺さっているからだ。「"良い材料から良い紙ができるのは当たり前、足元に転がっている雑草やゴミに魂を吹き込む仕事をしろ"と言われました。それを実現しようと、今も試行錯誤しています」と潤平は語った。
ubusuna IZA prototype の下げ札に使われている和紙は、八代市で400年以上にわたって受け継がれてきた「宮地手漉き和紙」の道具を使って、一枚一枚、潤平が漉いたもの。その手触りは繊細で柔らかく、自然の温かみを感じる。同時に印象に残るのは、植物繊維のもつ強靭さだ。軽やかなのに存在感がある。この感覚は、手漉き和紙ならではなのだろう。 潤平のパートナー、金刺宏子が水俣生活学校に初めて足を踏み入れたのは24歳のとき。自然の中で昔の人のように衣食住を賄うというコンセプトに共鳴し、この地を訪れた。米や野菜を育て牛を飼うという自給自足の生活の中で、水俣の農家とも交流し、「生きる哲学」を学ぶ。機織りもその延長線上にあった。
宏子が機織りと出会ったのは、1992年に水俣生活学校が幕を下ろした直後のことだった。近所の集落の人から機織り機を譲り受けたものの、最初は機織りにピンと来ていなかったと言う。 「機織りは、美術大学に行ったような人がやるものだと思っていたんですね。でも、実際はそうではなくて、昔は普通の人が自分たちの着る物を織っていた。それなら私にもできると思い直したんです」 単純に見えて経験と熟練の技が必要な機織りは、昔の地域の女性にとって心の拠り所だったのではないかと、宏子は考えている。地道な手仕事を通して、女性たちが自己の存在価値を実感していた時代が、水俣には確かにあったのだ。しかし、時間と手間がかかる機織りは、時代の流れとともに失われていく。その中で機織りから離れてしまった女性の哀しみも感じながら、宏子は手仕事に臨んでいるのだと言う。
ある時、宏子は、機織りを教わりに行った家で、貴重な和綿「伯州綿」の種を手に入れる。元来、畑の作業が好きだったので、早速畑に種を蒔き綿を育てることに。その綿は、「肥後木綿」として再生した。今回、肥後木綿を手で紡ぎ、手織りしたテキスタイルは、産土の服で活かされることになる。 「産土の服は私たちの仕事に光を当ててくれる。時間のかかる手仕事によって作られる産土の服は、新しい時代に則したものづくりの形だと思います。ただ古いものを守るだけではなくて、新しい文化として打ち出していく。そこに共感しています」 そう言って宏子は笑顔を見せた。(2024年10月31日時点での記事)
水俣浮浪雲工房は、手漉き和紙と草木染めの手織り布を主に製造している。ある日工房を訪ねると、土間では代表の金刺潤平が昔ながらの道具で紙を漉いていて、奥の部屋からは「タンタン」という音が聞こえてきた。潤平のパートナーでもある金刺宏子が機を織っている音だ。
この工房は、胎児性及び幼児性水俣病患者に生きる糧を与えることを目的に1982年に創設された、自給自足型のフリースクール、水俣生活学校が原型である。潤平は、東京の大学を卒業すると同時に、ボランティアとして水俣生活学校に参画するために水俣の地を踏んだ。紙漉きを始めたのは、詩人、作家、そして環境運動家として知られる石牟礼道子氏のアドバイスによるものだ。
「水俣病の子供達でもできる仕事を作るという一念で紙漉きを始めたのですが、それではなかなかお金は稼げないわけですよ。そんななか、道子さんは、いろんな面で、ずっと活動をサポートしてくれました。僕らが自分たちの手仕事で生きていけるようになって、一番喜んでくれたのも道子さんでした」 それから時が流れた2015年、潤平は、石牟田氏の推薦により、当時の天皇皇后両陛下がご使用になった和紙のグリーティングカードを制作している。
潤平は紙漉き以外にもイノベイティブな才能を発揮。イグサの製紙原料繊維化技術に成功したほか、立体紙を考案したりと仕事のフィールドを広げてきた。また、ウズベキスタン・サマルカンドのシルクペーパーの復元など、その活動の場は国境をも越えている。 それでも彼は、今日も水俣の地で紙を漉く。それは、作家、水上勉氏にかけられた一言が心に刺さっているからだ。「"良い材料から良い紙ができるのは当たり前、足元に転がっている雑草やゴミに魂を吹き込む仕事をしろ"と言われました。それを実現しようと、今も試行錯誤しています」と潤平は語った。
ubusuna IZA prototype の下げ札に使われている和紙は、八代市で400年以上にわたって受け継がれてきた「宮地手漉き和紙」の道具を使って、一枚一枚、潤平が漉いたもの。その手触りは繊細で柔らかく、自然の温かみを感じる。同時に印象に残るのは、植物繊維のもつ強靭さだ。軽やかなのに存在感がある。この感覚は、手漉き和紙ならではなのだろう。
潤平のパートナー、金刺宏子が水俣生活学校に初めて足を踏み入れたのは24歳のとき。自然の中で昔の人のように衣食住を賄うというコンセプトに共鳴し、この地を訪れた。米や野菜を育て牛を飼うという自給自足の生活の中で、水俣の農家とも交流し、「生きる哲学」を学ぶ。機織りもその延長線上にあった。
宏子が機織りと出会ったのは、1992年に水俣生活学校が幕を下ろした直後のことだった。近所の集落の人から機織り機を譲り受けたものの、最初は機織りにピンと来ていなかったと言う。 「機織りは、美術大学に行ったような人がやるものだと思っていたんですね。でも、実際はそうではなくて、昔は普通の人が自分たちの着る物を織っていた。それなら私にもできると思い直したんです」 単純に見えて経験と熟練の技が必要な機織りは、昔の地域の女性にとって心の拠り所だったのではないかと、宏子は考えている。
地道な手仕事を通して、女性たちが自己の存在価値を実感していた時代が、水俣には確かにあったのだ。しかし、時間と手間がかかる機織りは、時代の流れとともに失われていく。その中で機織りから離れてしまった女性の哀しみも感じながら、宏子は手仕事に臨んでいるのだと言う。
ある時、宏子は、機織りを教わりに行った家で、貴重な和綿「伯州綿」の種を手に入れる。元来、畑の作業が好きだったので、早速畑に種を蒔き綿を育てることに。その綿は、「肥後木綿」として再生した。今回、肥後木綿を手で紡ぎ、手織りしたテキスタイルは、産土の服で活かされることになる。 「産土の服は私たちの仕事に光を当ててくれる。時間のかかる手仕事によって作られる産土の服は、新しい時代に則したものづくりの形だと思います。ただ古いものを守るだけではなくて、新しい文化として打ち出していく。そこに共感しています」 そう言って宏子は笑顔を見せた。(2024年10月31日時点での記事)






全ての服のどこかに使われる肥後木綿
ubusuna IZA prototypeの全ての服の一部に、再生した肥後木綿が使われている。それは、産土の服の「魂」と言ってもいいだろう。肥後木綿は今後のコレクションでも、柄を変えて、服のどこかに使用される。
ubusuna IZA prototypeの全ての服の一部に、再生した肥後木綿が使われている。それは、産土の服の「魂」と言ってもいいだろう。肥後木綿は今後のコレクションでも、柄を変えて、服のどこかに使用される。

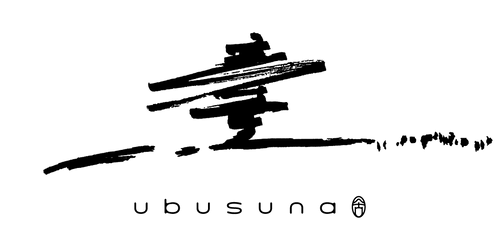
© ubusuna 2024 Furushohonten